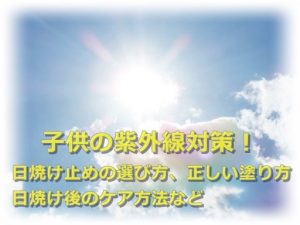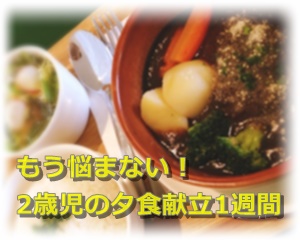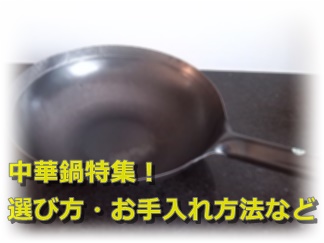おすわりやハイハイが上手にできるようになったり、つかまり立ちができたり。
生後9~11ヶ月頃になると、運動能力も発達してきて、
目に見える成長を感じられるので、嬉しい時期ですよね。
・・一方、良いことばかりではなく、離乳食に関しては、
食欲に大きくムラがあったり、遊び食べが始まったり、、
そんな悩みに差し掛かる頃でもあります。
そこで今回は、嬉しい!&困った!が連続の、
離乳食後期の進め方について。
量の目安やメニューの提案と共に、私が実践して効果のあった、
離乳食つくりの負担を軽くする工夫や、遊び食べの対策もまとめました。
毎日の離乳食つくりに、負担を感じているあなた、
遊び食べに悩まされているあなたのお役にたてるハズです!
離乳食後期の進め方一覧表
| 1日3回。 授乳と離乳食を、徐々に置き換えていきます。 離乳食後の授乳は必要ありませんが、赤ちゃんが欲しがるようならあげても大丈夫。 大人と同じ朝・昼・夜と同じタイミングにして、食事リズムを整えていきましょう。 |
|
※参考資料・・・厚生省「離乳食の進め方の目安」
|
|
|
|
| 料理によって、塩、砂糖、醤油、バター、チーズなどで味付け。 マヨネーズは生卵が入っているので、アレルギーのある場合は注意。 味付けは、薄味を心がけます。(大人の半分くらい) |
|
|
離乳食後期~見た目の量はどのくらい?
ご飯や野菜などのグラム数は、上の表で分かりますが、正直数字だけだと、実際見た目にはどのくらいの量になるのか、
想像がつきにくいですよね。
そこで、参考までに、
生後9~11ヶ月の間に、うちの子がよく食べていた離乳食を紹介したいと思います!

(生後9ヵ月頃)
|

(生後10ヶ月頃)
|

(生後11ヶ月頃)
|

(生後11ヶ月頃)
|
うちの子は、スープにすると野菜をたくさん食べてくれていたので、
スープメニューが多いのですが・・・m(__)m
スープは、野菜はもちろん、魚やお肉もお団子にして入れられるし、
味付けも和・洋・中、様々な工夫ができます。
量の調節もしやすいし、
たくさん作って冷凍することもできるので、とっても便利ですよ。
離乳食作りの負担を軽くする3つの工夫
離乳食は、月齢によってあげる目安量が少しずつ変わってくるし、調理に手間もかかるし、正直、結構大変(p_-)
離乳食以外に、大人の食事も用意しないといけないし、
毎回グラムをはかって・・というのは、あまり効率が良いとはいえませんよね。
そこで、なるべく負担を軽くする工夫をしましょう♪
実際に私がやっていた方法は、
- 一番初めだけきちんと量をはかり、その後は目分量で
- 冷凍できるものはたくさん作って、1食分ずつフリーザーパックに入れて冷凍
- 疲れたときは、市販のベビーフードに頼る
やっぱり、毎回食事の量をはかるというのは、かなりの手間。
私は、一番初めはグラムをはかって、だいたいの目分量を覚えたら、
次からはその目分量で、あげていました。
赤ちゃんの体調や機嫌によって、よく食べる日やあまり食べない日もあるので、
多少のプラスマイナスは、あまり気にしませんでした。
また、野菜スープや豚汁などの汁ものは、一度にたくさん作って、
1食分ずつフリーザーパックに入れて冷凍します。
食べる前に、鍋にあけて温めるだけなので、忙しいときには楽できますよ♪
そして、時間のないときや、疲れていて離乳食を作る元気がないという時には、
無理せず、市販のベビーフードを利用するのも手です。
普段作らないメニューがあったり、見た目の量など、参考になることも多いです。
3~4つ常備しておくと、いざという時に役立ちますよ。
赤ちゃんの遊び食べ!対策はどうする?
この頃になると、自立心が芽生えてきて、一人で食べようという意欲が出てきます。手の動きもしっかりしてくるので、
なんでも手を出しては、グチャグチャと食べ物で遊びだしてしまうことも(p_-)
テーブル周りが汚れたり、なかなか食事が進まなくて、イライラしちゃいますよね。
でも、遊び食べは、
一口に入る量や、食べ物の食感を学習していくのに大切な過程!
できるだけ、自分で食べようとする意志を大切にして、
しかったりせず、見守るようにしたいです。
その時は、椅子の下に新聞紙やビニールシートなどを敷いておくと、
後片付けが楽ですよ。
うちは、リビングの床がフローリングなので、食べこぼしが染みにならないよう、
IKEA のフロアプロテクターを敷いています。

ただし、遊び食べに対しては、食事の時間20分前後で切り上げるようにするのが◎
「もうそろそろ片づけようね」と声掛けをして、あっさり片づけるようにします。
離乳食後期に気を付けること
最後に、この時期の食事で気を付けたいことを、紹介します。1.しっかり噛む癖をつける
生後10~11ヶ月頃になると、自己主張が出てきて、
お腹が空いていると、次の一口を急かされることがあります。
でも次々に食べ物を口に放り込まず、今の時期から噛む癖をつけさせておくと、
将来の、食べ過ぎや虫歯予防につながりますよ。
赤ちゃんの機嫌が良いときに、一度、口の中を観察してみてください。
奥の歯茎に、ふくらみと幅がでてきているのが、分かるはず!
その歯茎で食べ物を噛めるようになるのが、この時期の目標です。
食べ物を口に入れた後、あご・舌・唇を動かしていれば順調な証拠(^O^)♪
「モグモグ」「ゴックン」と声掛けをしながら、大人が見本を見せると、
真似をしてくれるので、食事の時間はゆったりととっていきたいですね。
2.自分で食べようとする意欲を尊重する
自分でスプーンやフォークを持てるようになると、
大人の真似をして、自分で食べたがるようになります。
でも、お皿に入ったものをすくい取って、口に運ぶのはまだ難しいので、
癇癪(かんしゃく)を起こして、泣いちゃうことも・・
そんな時は、
子供にはスプーンを持たせて、少量の食事を子供用の器に入れて自由にできるようにします。
その合間に、大人が別のスプーンで食べさせてあげましょう。
一生懸命自分で食べようとしつつ、お腹も満たされていくので、赤ちゃんも満足(*^_^*)
パンやおにぎりなど、手づかみできるものは、手にもたせておくのもいいですね。
赤ちゃんは失敗を重ねながら、成長していくもの。
スプーンやフォークをうまく使えないところを見ていると
やきもきしちゃいますが、おおらかな気持ちで見守ってあげたいです。
3.コップで水を飲む練習をする
コップで水分を飲むことで、コップのフチを唇でとらえる力が発達していきます。
マグマグなどで飲み続けるクセがつくと、唇の機能が成長しません。
嫌がる様子がなければ、家にいるときにはコップで水をあげてみましょう!
さいごに
いかがでしたか?食べる量は、赤ちゃんの気分しだい、ということも多々ありますが、
生活リズムを整えて、食事の時にちゃんとおなかが空いている状態にしてあげるのも、
お母さんの大切な役目だと思います。
あともう少しで、大人とほぼ一緒のものが食べられるようになりますよ。
頑張ってくださいね!